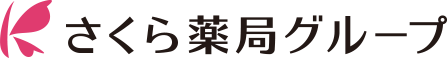2025.03.03
第95話 漢方薬剤師が勧める大根の食べ方
新型コロナウイルスが最盛期だった2021年正月、コロナに勝つレシピを紹介しました(第70話)。亜鉛(牡蠣)、ナイアシン(深煎りコーヒーまたはヒラタケ)、ビタミンD(キクラゲ)が三種の神器になって、自然免疫力アップに役立ちます。しかし科学は日進月歩、ナイアシンの替わりにトリゴネリンというコーヒー生豆の成分を飲めば、それがナイアシンになって、更には免疫力を高めるNAD(ニコチナミドアデニンジヌクレオチド)になることが分かったのです(文献1)。
そのトリゴネリンを最も多く含んでいるのはコーヒーの生豆ですが、桜島大根やハーブ・フェヌグリークにも含まれていることが分かっています(第89話を参照)。残念なことに普通の大根には少ししか含まれていません。しかし大根の辛味成分には単独でも免疫力アップの作用があるらしいので、身の回りの身近な野菜として、毎日でも食べる予想を超える好ましい効果を生むかも知れません。
そこで今回は、漢方薬が専門の薬剤師さんが書いたブログから、大根で免疫力アップの珍しい食べ方を3つ紹介しましょう。どの食べ方にも漢方理論の説明が成り立つのだそうです。
先ず初めに「なぜ大根なのか」について簡単に説明しておきます。胃腸が疲れて食欲がなくなると風邪を引きやすいことは誰もが経験しています。では胃腸が疲れるとなぜ風邪にかかりやすくなるのでしょうか?答えは、体力を維持するためのエネルギーの素が摂れなくなるからです。簡単に言えば、栄養不足ということで、体力だけでなく免疫力も不足してしまいます。食べ物の消化吸収ができなくなると病気になります。それほどに胃腸の働きは重要だということです。ですから、胃腸の健康を保ち、栄養をしっかり摂っていれば、体力も免疫力も維持されて、風邪にもインフルエンザにもかからない丈夫な身体になってくれるのです。同じ満員電車で通勤していても、感染症にかかる人とかからない人がいるのは、胃腸の健康の差とも言えるのです。
では、胃腸の健康を立て直すために古くから伝わっている漢方風の大根の食べ方を紹介します。大根は天然の胃腸薬とも言われている野菜でもあるのです。
その①大根おろし
これは誰もが知っているオーソドックスな生の大根の食べ方です。「お腹の調子が悪いな」と感じたら、その日の食事で「大根おろし」を食べましょう。大根おろしは最も身近な消化薬で、有効成分はアミラーゼという消化酵素です。胃腸の働きを助けて、胃もたれや胸やけなどの症状を抑えます。お餅を大根おろしで食べると胸やけしないとも言われています。
大根の辛味成分はイソチオシアネートで、すりおろして空気に触れると辛味が出ます。イソチオシアネートは抗酸化成分で、肝臓の働きを助けて解毒作用を高めます。しかし加熱すると直ぐに揮発して無くなってしまいます。辛味を効率よく摂るには、食べる直前にすりおろすのがよいのです。
大根にはビタミンCも多く含まれています。これも火を通すと減ってしまうので、生で食べるのが一番です。
その②はちみつ大根
日本薬局方にも収載されている「ハチミツ」(注意1)には、咳止め効果が知られています。はちみつをコーヒーに入れて飲むと、その咳止め効果はステロイド剤や市販の咳止めよりも強いとの臨床試験データが報告されています(文献2)。はちみつ大根は昔から伝承されてきた民間薬なので臨床試験はありません。本当に効き目があるのでしょうか?
のどの痛みから風邪がはじまる人が多いのですが、食べ物を飲むのが辛くなるほどの痛みがあると、食べる気もしなくなって、体力が落ちてしまいます。のどの痛みを和らげたり、予防するのがはちみつ大根で、昔からある民間療法です。いまではそういう食べ方はほとんどなくなりましたが、ブログを書いた薬剤師さんが自ら試してみたところ、驚くほど効果を感じたそうです。
1つ注意することは、はちみつ商品には色々あるので、どれが良いのか迷ってしまうでしょう。そこで筆者がお勧めするのは、混ざり物が無くて割安で熱処理していない「日本薬局方のハチミツ」です。詳しくは薬局でお聞きください。
作り方は簡単で、まずは大根を1センチ角に切ってガラス瓶かタッパーに並べて、はちみつは大根の8分目程度に加えます。そのまま一晩置いておくと、大根から浸み出た水とはちみつが混ざり合って、水分の量が増えてきます。その大さじ1杯をゆっくり舐めるように飲むのがコツです。
残った大根は料理に使っても良いですし、甘いのでそのまま食べても美味しいと思います。
その③梅流し
お通じの調子が悪くなりかけたときに「梅流し」という食べ方が効くことがあります。材料は、大根2分の1本、梅干し2〜3個、昆布1枚(なくてもよい)です。
作り方は、大根を1センチ程度に輪切りにし、1リットル程度の水で柔らかくなるまで煮ます。皮はむいてもむかなくてもいいですが、皮にも栄養素が多く含まれているので、皮ごと使うのがお勧めです。大根が軟らかくなったら、昆布を取り出して完成。柔らかくなった大根を梅干しとともに食べるのが、梅流しと呼ばれる食べ方で、結構美味しいものです。
大根1切れに適当な量の梅干しを載せて、先ずは食べてみましょう。多くの人が1〜2時間後に便意を催して、スッキリするようです。もしそうならなかったら、もう1切れを食べて様子を見ることです。昔からの言い伝えがどのくらい効くものなのか、チャンスがあったら是非試して下さい。
文献1: Membrezt M, et al. Trigonelline is an NAD+ precursor that improves muscle function during ageing and is reduced in human sarcopenia. Nat Metab 6:433-47, 2024.
文献2: Raeessi MA, et al. Honey plus coffee versus systemic steroid in the treatment of persistent post-infectious cough: a randomised controlled trial. Prim Care Respir J 22:325-30, 2013.
注意1: ハチミツは生後1歳未満の乳児には食べさせないでください
消費者庁ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/microorganism_virus/contents_001