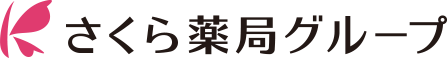2025.05.01
第96話 プロバイオティクスとプレバイオティクス
肝臓、腎臓、心臓、更には脳と言ったような、身体のあちこちの健康状態に「腸の健康」が係わっているとのことです。昔から「腹も身のうち」というように、腹具合が悪いと元気が出ないし、便秘をすると肌が荒れやすくなることもよく知られています。そのため整腸薬は家庭の常備薬としている家庭も多いです。
腸とその他の臓器との関係を少し詳しく調べてみました。腸の健康は腸内環境で決まります。腸内環境とは、善玉菌と悪玉菌の勢力関係で決まるとのことです。善玉と悪玉の間を取り持っているのが日和見菌で、善玉か悪玉かどちらでも数の多い方に味方するのだそうです。そこで、善玉菌が増えるような飲み物や食べ物、あるいは一般用医薬品やサプリメントが売り上げを伸ばしているのです。逆に悪玉菌を減らすような薬もあって良さそうですが、今のところ見当たりません。
善玉菌を増やす方法には大きく分けて2つあります。1つはプロバイオティクスで、これは善玉菌そのものの製品のことです。先ず医薬品としては、乳酸菌製剤(ビオフェルミンなど)、ビフィズス菌製剤(ラックビーなど)、酪酸菌製剤(ビオスリーなど)があります。どれも古い薬ですが、処方薬として今も健在です。抗生物質を飲んだ後に善玉菌を補給するとか、高熱が続いてお腹の具合が悪いときに良いと言われています。次に、プロバイオティクスの食べ物としては、日本の伝統食品である味噌、納豆、ぬか漬け、甘酒、コンブ茶など、また韓国のキムチも日常よく見かけるプロバイオティクスです。更に飲物としては、乳酸菌飲料(カルピスやヤクルト)とヨーグルトドリンク(多くの商品がある)があります。ただし、これらの発酵食品には繊維質が含まれていることが多いので、薬のように純粋なプロバイオティクスではなくて、後述するプレバイオティクスの一面も持ち合わせているのです。
ここで大事なことは、医薬品でも食品でも、プロバイオティクスには大きな欠点があるということ。つまり、「摂った時だけの一時的な効果で、摂り続けなければ効き目は数日で消えてしまう」ということです。個人ごとに大きく異なる腸内細菌の善玉/悪玉バランスは、そう簡単には変えられないということです。食べ物の場合は、例えば納豆に多く含まれている納豆菌は枯草菌の仲間ですから、人の腸内菌ではありません。ですから人の腸に住み着くということはありません。キムチの場合には乳酸菌なので、人の腸に住んでいる善玉菌の仲間です。たまにキムチを食べたとしても、人それぞれの異なる種類の乳酸菌が増える訳ではないのです。
そこで最近よく耳にするのが、プレバイオティクスです。分かり易く言いますと、「善玉菌の餌」ということで、食べた人には消化できなくても、その人の腸に住んでいる善玉菌の餌になって、それを食べた善玉菌が増えるということです。善玉菌の餌となる食品とは、人の消化液では消化されないか、または消化され難い線維性食品のことです。健康との関係で前世紀から言われていたことは、繊維性食品を食べるとお通じが良くなるということでした。それに比べて、腸内菌と身体中の臓器との関係が解明されて、その健康効果がPRされるようになったのは、実は今世紀になってからのことなのです。
腸内の善玉菌について、今世紀の新たな発見は、善玉菌が繊維質の餌を食べて作る小さな分子の働きです。これらの小分子が腸壁の細胞と、その周辺に住んでいる炎症性マクロファージに働きかけて、過剰な免疫反応と炎症を抑えているというのです。そのお陰で、お通じは兎も角として、炎症性腸疾患である過敏性大腸炎やクローン病を予防するし、大腸癌のリスクも下げるのだそうです。大規模な疫学調査によって、善玉菌を増やす野菜や果実を多く食べている人は、こういう病気になり難いというデータが世界各国から出ています。そして、子供のうちから食習慣に気を配って、線維性食品を多く摂る習慣を身に着けることが、成人してからの生活習慣の維持に大いに役立つというのです。
さらに重要なことは、善玉菌の働きは、腸の病気だけでなく、その他の臓器の健康にも大きな影響を及ぼすことです。疫学研究でも「腸とその他の臓器の関係」を示すデータがどんどん増えています。腸と脳の関係は特に注目されていて、これまでとは一味異なる認知症の予防/治療も研究されています。中でも特に善玉菌が作る小さな分子のナイアシン(ビタミンB3)と酪酸(低級脂肪酸)が注目されています(文献1)。この2つの分子はどちらもGPR109Aという腸管細胞表面の受容体に結合して、腸の炎症を鎮め、過敏性大腸炎を予防します。それだけでなく、血管を通じて全身の臓器に届けられて、そこにある受容体GPR109Aを刺激して炎症を予防しているのだそうです。これらはプロバイオティクスを遥かに超える効き目と言えそうです。
最後に、プレバイオティクスの効き目を相乗的に強める生活習慣について書いておきます。先ずはストレスを減らして十分な睡眠をとること、次に規則正しい食事、そしてとりわけ大事なのが適度な運動ということです。筆者は毎日の買い物で4,000歩以上を心掛けているところです。
文献1. Singh N, Gurav A, et al. Activation of Gpr109a, receptor for niacin and the commensal metabolite butyrate, suppresses colonic inflammation and carcinogenesis. Immunity 40: 128-39, 2014.