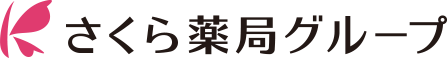2025.09.01
第98話 ベタインの魅力
栄養成分としてのベタインをご存知ですか?タウリンがあまりに有名なためか、タウリンを含む食品に同じように含まれているベタインの影は霞んでいます。カニやタコなどの魚介類・・・美味しい日本食の素材にはタウリンが多く含まれています。それと寄り添うようにべタインも入っているのです。言い換えれば、タウリンを摂ろうとすれば、ごく自然にベタインも摂れるのです。1つだけの例外はホウレン草でベタインを多く含んでいますが、タウリンはほとんど入っていません。ホウレン草は不思議な野菜で、ベタインが最初に発見されたのは魚介類ではなくホウレン草だったのです。
筆者が小学生の頃、「ホウレン草の栄養素はビタミンA、根本の赤い部分を残さず食べなさい」と習いました。今と違ってビニールハウスでの栽培法は無かったのですが、元々寒さに強い野菜なので冬の路地でも枯れることなく、青さを保ちます。今思うとベタインのおかげかもしれません。直接的な因果関係はまだ研究段階のようですが、一般論として植物生理学的にベタインは寒冷ストレス耐性に役立つことが知られています。
ベタインはタウリンと同じように「オスモライト(浸透圧調節物質)」として大切な栄養素です(第97話も参照)。植物でも動物でも、細胞内の水分保持や、タンパク質を安定化し、乾燥・塩害・低温などのストレスから身体を守っています。ホウレン草の「寒じめ栽培(ちぢみホウレン草)」では低温による代謝調整が起こり、結果としてベタインが増加するようです。一方、魚介類にタウリンやベタインが多い理由は明らかで、塩濃度の高い海中で塩漬けにならないように生きるにはオスモライトが必要なのです。人の場合にもタウリンやべタインは欠かせません。例えば腎臓の例が有名で、食塩や尿素をろ過する糸球体では、血液と尿の浸透圧の差をものともせず、塩漬けにもならずに頑張れるのです。
タウリンとベタインはよく似たオスモライトなのですが、物質代謝の面から見ると大きな違いがあります。「ベタインはメチル基供与体である」ということです。炭素原子をたった1つしか持たないメチル基(—CH3)の代謝は、学術的には「1炭素代謝」として注目されています。では、1炭素代謝を分かり易くバトンリレーに例えて説明してみましょう。メチル基は、バトンリレーのバトンのように次から次へと、分子から分子へ受け継がれて、最後にテープを切るのは、遺伝子、タンパク質、ホルモンのような、健康にとって極めて重要な働きをする分子との出会いです。これらの分子は身体が「働きなさい」と要求したときだけ働いて、そうでないときは静かに眠っていなければなりません。分子のメチル化とは、分子を静かに眠らせておくことなのです。
ところがごく最近になって、何かの原因でメチル基が不足すると全身の臓器の働きが狂ってしまって、場合によっては病気を起こすことが分かってきました。特に高齢者に多く見られる病気として、筋肉の衰え、心臓病、腎臓病、肝臓病、肥満、糖尿病、脳神経疾患、がんなどの原因が、それら臓器のメチル化の異常によるというのです。言い換えると、バトンリレーの最終走者であるSAM(S-アデノシルメチオニン)の不足が原因になっているとのことです(文献1)。
そこで言えることは、メチル基を補給する食べ物を食べてバトンランナーにメチル基というバトンを持たせれば、病気を予防できるということです。妊婦に不足し易い栄養素がビタミンB群の葉酸やB12であることはよく知られています。これらはどれもリレーコースの構成要素です。ですから不足を予防するには、葉酸はホウレン草、B12は魚介類や鶏卵を摂るなど、食事を工夫すれば予防可能ですし、ベタインを多く含む魚介類を加えれば、薬食同源を満足できるようにもなるのです。
では最後に分かり易い例を引いて効き目の原理を説明しましょう。皆さんもよく知っているストレスホルモンの1つアドレナリン(エピネフリン)の場合です。誰でも何かにびっくりしたり興奮したりすると、副腎と言う臓器からアドレナリンが分泌されます。このホルモンは、興奮状態に対応するエネルギーを生み出す役目を果たすのですが、興奮が長引くと疲弊してしまいます。そうならないように、アドレナリンが分泌されるとすぐさまSAMが働いて、アドレナリンはメチル化されて作用が消えてなくなるのです。そして興奮した本人は「ああビックリした」と言って、間もなく興奮状態から覚めてしまいます。身体の至る所で、これと似たSAMの働きが見られます。そしてもしSAMが枯渇してメチル化に支障が起こると、誰しもが色々な病気にかかってしまうのです。
文献1) Park J, Shin EJ, et al. Exploring NNMT: from metabolic pathways to therapeutic targets. Arch Pharm Res 47(12):893-913, 2024.